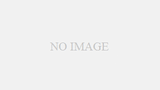最近、ちょっとしたことでイライラしたり、不安に飲み込まれてしまったりしていませんか?現代はストレス社会。だからこそ「情緒が安定している人」ほど、仕事も人間関係も上手くいくんです!この記事では、情緒が不安定になる原因から、今日からすぐ実践できるメンタルの整え方までを徹底解説。不安やイライラに振り回されない、自分らしく穏やかに過ごせるコツをお伝えします!
情緒が不安定になる原因とは?心が揺れやすい人に共通する思考と生活習慣
情緒が不安定な状態って、なんとなく「落ち着かない」「すぐにイライラする」「不安が止まらない」っていう感じで、自分でもうまくコントロールできないことが多いですよね。でも、その揺れやすさにはちゃんと理由があるんです!ここでは、情緒が不安定になる根本的な原因と、心が揺れやすい人に共通する思考パターンや生活習慣を、具体的に解説していきます。
⸻
思考のクセが「情緒不安定」を引き寄せる
まず知っておいてほしいのが、情緒が不安定な人には共通する“思考のクセ”があること。代表的なのが次のような思考パターンです。
• 完璧主義:「こうでなきゃダメ」と理想が高く、少しの失敗でも強く落ち込む。
• 自己否定的な内省:「私が悪い」「私なんて…」と、すぐに自分を責めてしまう。
• 先読み不安:「どうせ上手くいかない」「これから悪いことが起きる」と未来を悲観的に想像する。
• 過剰な自己コントロール欲求:「自分でどうにかしないと!」と、抱え込みやすい。
これらの思考パターンは、脳が常に緊張やストレスを感じている状態を作り出します。そして、その積み重ねが“感情の揺れ”につながるんです。
⸻
睡眠・食事・運動…生活リズムの乱れが心を不安定にする
次に注目したいのが「生活習慣」。思考だけじゃなく、毎日の過ごし方も情緒に大きく影響しています。例えば…
• 睡眠不足:脳の回復が不十分になると、感情のコントロール力が激減します。
• 血糖値の乱高下:甘いものや炭水化物中心の食事ばかりだと、血糖値が乱れてイライラしやすくなります。
• 運動不足:運動にはストレスホルモン(コルチゾール)を減らす効果がありますが、運動習慣がない人は感情が滞りやすくなる傾向があります。
• スマホの使いすぎ:SNSやニュースを見すぎることで、比較・焦燥・不安が無意識に蓄積されます。
「なんとなく調子が悪いな…」という日が続いている人は、まずこの生活リズムの見直しから始めるといいかもしれません。
⸻
過去のトラウマや環境要因も影響しているかも?
情緒不安定の背景には、**過去の傷つき体験(トラウマ)**が潜んでいる場合もあります。たとえば…
• 幼少期に親から否定され続けてきた
• 恋愛や人間関係で強い裏切りを受けた
• 失敗や挫折の経験から「どうせまた…」と過度に警戒してしまう
これらの経験が“心のベースの不安”を作り、日常の小さな刺激にも過敏に反応してしまうことがあります。
また、職場や家庭の人間関係、経済的な不安、孤独感といった環境要因も、情緒を大きく揺らす要因になります。こうした外部要因に振り回されることで、自分の中にある「安心の土台」が失われていくのです。
⸻
情緒が不安定な人の典型的な習慣5つ
最後に、日常的にやってしまいがちな「情緒不安定を引き寄せる習慣」を5つ紹介します。
1. ひとり反省会が長すぎる:夜に布団で過去の出来事を何度も思い出してしまう
2. 人の評価を気にしすぎる:「どう思われたかな…」が口ぐせになっている
3. 悩みを溜め込む:弱音を吐けず、全部ひとりで処理しようとする
4. 完璧を求めて疲弊する:つねに「もっと頑張らなきゃ」と追い込んでしまう
5. 自己ケアを後回しにする:自分の体調や気持ちに鈍感で、無理しがち
こうした習慣に思い当たる節があるなら、まずは「それ、やめてもいいんだよ」と自分に優しく声をかけることから始めてみてくださいね。
不安・イライラを引き起こす脳とホルモンの仕組みを理解しよう
感情の揺れって、性格だけの問題じゃないんです。不安やイライラが止まらなくなる背景には、ちゃんと「脳」と「ホルモン」の仕組みが関係しています。つまり、メンタルが不安定になるのには“身体的なメカニズム”があるということ。これを理解することで、自分を責めるのをやめられたり、「どう対処すれば落ち着けるのか」が見えてきますよ!
⸻
脳内で感情を司る“扁桃体”と“前頭前野”の役割とは?
まずは脳の中でも、感情のコントロールに深く関わる2つの領域を押さえておきましょう。
• 扁桃体(へんとうたい)
→ 恐怖・怒り・不安などの「危険を察知するセンサー」の役割。強いストレスやトラウマがあると、この部分が過敏に働いてしまいます。
• 前頭前野(ぜんとうぜんや)
→ 感情をコントロールしたり、理性的な判断をする部分。扁桃体の暴走を抑える「ブレーキ役」と言えます。
情緒が不安定なときは、この扁桃体が過剰に反応しやすくなっていて、前頭前野のブレーキが効かない状態なんです。つまり「わかってはいるけど、止められない」という感じですね。
⸻
ストレスホルモン「コルチゾール」と不安の関係
イライラや不安を感じるとき、体内ではストレスホルモンの代表格「コルチゾール」が分泌されています。これは本来、危機に備えるための“防御システム”なのですが、慢性的に分泌されすぎると以下のような悪循環に。
• 睡眠の質が下がる
• 血糖値が不安定になってイライラしやすくなる
• 免疫力が落ちて体調も崩しやすくなる
• セロトニンやドーパミンの分泌が抑制され、やる気が出ない・気分が落ち込みやすい
つまり、ストレスを放置していると「感情面」「体調面」どちらも悪化していくということなんです。
⸻
幸せホルモン「セロトニン」「オキシトシン」が不足しているかも?
不安やイライラに効く“自然の鎮静剤”とも言えるのが、「セロトニン」と「オキシトシン」というホルモン。
• セロトニン:心のバランスを整える作用があり、幸福感や安定感をもたらす
• オキシトシン:人とのふれあいや信頼関係から分泌され、「安心感」や「親密さ」を強めるホルモン
これらが不足すると、どんなに周囲が平穏でも「なぜか不安」「ちょっとしたことで涙が出る」など、情緒の乱れが起こりやすくなります。
セロトニンが不足する原因には、運動不足・日光不足・朝食抜きなどが挙げられます。オキシトシンは、孤独な時間が長すぎる・スキンシップがない・人とのつながりが薄いと分泌が低下してしまうんです。
⸻
「女性ホルモンの波」が情緒不安定に影響することも
とくに女性の場合は、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンのバランスが、情緒の浮き沈みに大きく影響します。
• **エストロゲン(卵胞ホルモン)**が多いとき:気分が明るく、活力が湧きやすい
• **プロゲステロン(黄体ホルモン)**が多いとき:イライラ・不安・むくみ・落ち込みが出やすい
月経周期に合わせてこのバランスが変化するため、「なんか今日は情緒が不安定…」という日が定期的にやってくることも。この影響を自覚するだけでも、「今日の気分はホルモンのせいかも」と受け止めて、過剰に自己否定しなくて済むようになります。
⸻
情緒を整えるには「脳とホルモンを落ち着かせる習慣」が大事!
ここまで紹介してきたように、情緒不安定の根っこには脳の過敏さやホルモンの乱れがあることが多いです。だからこそ、「気合いでなんとかしよう」とするのではなく、次のような方法で“内側から整える”ことが重要です。
• 朝日を浴びて体内時計をリセットする
• セロトニンを活性化するリズム運動(ウォーキング・呼吸法など)を習慣にする
• オキシトシンを分泌するために、信頼できる人との会話やスキンシップを大切にする
• ホルモンバランスを整えるために、睡眠・栄養・ストレス管理を徹底する
自分の情緒を整える鍵は、「脳の使い方」と「体の整え方」、両方にアプローチすること!この視点があると、心の波に振り回されにくくなりますよ。
毎日のルーティンで整える!情緒を安定させる具体的な生活習慣7選
情緒の安定って、特別なことをしなくても“毎日のちょっとした習慣”の積み重ねで作られていくんです!実は、不安やイライラに悩んでいる人ほど「なんとなく過ごしてる時間」が多く、無自覚のうちに心が乱れやすい状態を作り出していることも…。逆に、日々のルーティンを少し工夫するだけで、驚くほど気持ちが穏やかになっていくこともあります。
ここでは「今日から取り入れられる情緒安定の生活習慣」を7つ、具体的に紹介します!ぜひ、自分のペースで1つずつ試してみてくださいね。
⸻
1. 朝日を浴びて「セロトニン」を活性化しよう!
情緒の安定に直結している「セロトニン」は、日光を浴びることで分泌が促されます。特に朝の光は、体内時計をリセットしてくれる効果もあり、気分の安定・睡眠の質UP・ホルモンバランスの正常化に役立ちます。
【ポイント】
• 起床後30分以内に5〜15分、窓を開けて外の光を浴びる
• 曇りの日でも効果あり!曇天でも太陽の光は室内照明の数十倍
• 散歩しながら朝日を浴びると、リズム運動との相乗効果でセロトニンUP!
⸻
2. 朝の「3分瞑想」で心に余白をつくる
感情がブレやすい人の特徴として、思考が常にフル稼働している状態があります。そこでおすすめなのが、朝の「マインドフルネス瞑想」。たった3分でも、思考のノイズがスッと落ち着き、1日のスタートを穏やかに整えることができます。
【やり方】
• 背筋を伸ばして椅子に座る
• 目を閉じて、ゆっくり呼吸に意識を向ける(吸う4秒→止める2秒→吐く6秒)
• 雑念が浮かんでもOK!ただ「戻ろう」と呼吸に意識を戻すだけでOK
⸻
3. タンパク質とビタミンB群を意識した朝食でメンタルを底上げ
朝食は「心の栄養補給タイム」!特に、感情を整えるセロトニンやドーパミンはタンパク質(トリプトファン)やビタミンB群から作られるため、しっかり摂ることで日中の気分が安定しやすくなります。
【おすすめの朝食例】
• 納豆ごはん+卵+味噌汁
• ヨーグルト+バナナ+ナッツ
• サラダチキン+全粒パン+チーズ
朝の食事で甘い菓子パンだけ…はNG!血糖値の乱高下で、午前中からイライラ&集中力低下の原因になります。
⸻
4. 情緒を整える「10分ウォーキング」習慣をつけよう
ウォーキングなどのリズム運動は、セロトニンを分泌させるうえで超有効!1日10〜15分歩くだけでも、気分が落ち着いて、前向きな思考に切り替わりやすくなります。
【実践アイデア】
• 通勤の一駅分を歩く
• 昼休みに外を軽く散歩
• 夜、スマホを置いて軽く歩いて気持ちのリセット
ポイントは、「歩くことに集中する」こと!呼吸や足の感覚を意識すると、瞑想効果もプラスされて一石二鳥です。
⸻
5. 「書く習慣」で思考と感情を整理する
頭の中にモヤモヤがたまると、不安やイライラが増えてしまうもの。そんなときは、ノートに書き出すことで気持ちがスーッと整理されていきます。
【効果的な書き方】
• その日の不安やイライラを自由に書く(誰にも見せない前提でOK)
• 「私は今、○○に対してこう感じてる」と感情を主語にして書く
• 感情だけでなく「じゃあ自分に何ができそう?」まで書けると前向きになれる
書くことで、「思考の交通整理」ができて、ぐるぐる悩み続ける時間がぐっと減っていきますよ!
⸻
6. SNSやニュースとの“接触時間”を意識的に減らす
現代の情緒不安定の原因としてかなり大きいのが、スマホによる情報過多ストレスです。SNSのネガティブな投稿、刺激の強いニュース、比較ばかりのタイムライン…知らず知らずのうちに、心を疲れさせてしまっているんです。
【対策】
• 朝起きて1時間はスマホを見ない
• SNSを開く時間を「朝・昼・夜の10分だけ」とルール化
• フォローリストを見直して、自分にとって不安や焦りを感じるアカウントは整理する
スマホとの距離感を見直すだけで、驚くほど心がスッキリしていきますよ!
⸻
7. 「眠る力」が心の土台!睡眠の質を高める工夫をしよう
情緒の安定において、睡眠はすべての基盤と言っても過言ではありません。寝不足になると、前頭前野の働きが鈍って感情のブレーキがきかなくなり、イライラしやすくなったり、不安に敏感になったりします。
【質を上げるコツ】
• 寝る90分前にお風呂で深部体温を上げておく
• 寝る前のスマホ・テレビ・強い光はNG(ブルーライトは覚醒を促します)
• 寝る前に深呼吸や軽いストレッチでリラックス
• 寝室の温度や湿度、香りにもこだわってみる
毎日7時間以上、しっかり眠れているかどうか。まずはここからチェックしてみてくださいね。
⸻
情緒の安定は「一気に変わるもの」ではなく、「毎日のちょっとした選択」の積み重ねでつくられていくもの。習慣が変われば、感情の波も自然と穏やかになっていきます!
感情に振り回されないための「思考の整え方」とセルフカウンセリング法
情緒が不安定になっているときって、「わかってるのに感情がコントロールできない…」「なんでこんなことで泣いてしまうの?」って、自分でも戸惑う瞬間があると思います。でも実は、そういう“感情の暴走”には、脳内で無意識に繰り返されている**「思考のパターン」**が大きく関係しているんです。
つまり、「感情」を変えようとする前に、「思考の整理」から始めるのがポイント!ここでは、感情に振り回されにくくなるための“思考の整え方”と、すぐに実践できるセルフカウンセリングの方法をご紹介します。
⸻
感情の「トリガー(引き金)」に気づくことから始めよう
例えば、同じ出来事が起きても、落ち込む人とすぐ切り替えられる人がいますよね?この差は、“起きた出来事”ではなく、それをどう「受け取って」「考えたか」によって生まれています。
これは心理学でいう認知(思考)→感情→行動という流れに当たります。
【例】
・上司に注意された
→「私はダメな人間なんだ」(思考)
→ 落ち込み、自己否定(感情)
→ その後の仕事もミスが増える(行動)
つまり、最初の“出来事”よりも、“それをどう解釈したか”が、感情の波を大きくしてしまっているんです。この「自分の思考パターン」に気づけるようになると、感情の揺れにブレーキがかけられるようになります!
⸻
思考の整え方①:事実と解釈を分けてみる
感情が不安定なときほど、「起きたこと」と「自分の捉え方」がごちゃ混ぜになりがち。まずはこの2つを分けて考える習慣をつけてみましょう!
【例】
・事実:LINEの返信が来ない
・解釈:「嫌われたのかもしれない」「何か怒らせたのかな」
→ 実際はただ忙しいだけかもしれないのに、勝手な想像で感情を乱していることが多いんです。
【実践法】
紙やスマホメモに、
• 「出来事」
• 「自分の解釈」
を分けて書いてみてください。これだけで頭の中がクリアになって、「それって本当にそうかな?」と、自然に視点が変わってきます!
⸻
思考の整え方②:「〇〇すべき」思考をやわらげる
感情が不安定になりやすい人に多いのが、「私はこうあるべき」「他人はこうしてくれるべき」という“べき思考”。
この思考に縛られると、自分にも他人にも厳しくなってしまい、イライラや落ち込みの元になります。
【例】
・「仕事は完璧にこなすべき」→ 少しのミスでも激しく自己嫌悪
・「恋人は私の気持ちを察すべき」→ 期待が外れて怒りや寂しさに変化
【置き換えフレーズ】
「~すべき」を「~だといいな」「~だったら嬉しいな」に変えると、気持ちがふわっと軽くなります。
⸻
思考の整え方③:「質問」で自分の思考にツッコミを入れる
不安やイライラで心がざわついているときは、冷静な視点を取り戻すために「自分への質問」が効果的!
【おすすめ質問例】
• それって本当に100%そうだと言い切れる?
• 他に考えられる可能性は?
• 10年後の自分はこれをどう見ると思う?
• 友達が同じことで悩んでいたら、私は何て声をかける?
こういった“思考の整理質問”を自分に投げかけてみると、暴走していた感情が自然に落ち着いていくことが多いんです。
⸻
セルフカウンセリング法:ノートで心を見える化しよう!
感情を安定させるために、もっともシンプルで効果的な方法のひとつが「書くこと」。とくに、次のようなステップで書き出す“セルフカウンセリングノート”がとってもおすすめ!
【3ステップで書くセルフカウンセリング】
1. 今の感情を書く:「悲しい」「モヤモヤする」「怒っている」など、正直に!
2. その感情の理由を書く:「○○と言われて傷ついた」「期待していたのに返事がなかった」
3. 自分がどうしたいのか?を書いてみる:「少し休みたい」「話を聞いてほしい」「距離を置きたい」
大切なのは、「いいことを書く」ことじゃなくて、「自分に正直になること」。感情を“頭の中”に溜め込むのではなく、“紙に出す”ことで、自然と気持ちが整理されていきます。
⸻
怒り・不安のピークをやり過ごす「緊急クールダウン術」
感情が爆発しそうなときは、考え方を整える前にまず**「クールダウンする技術」**が必要です。以下は、感情のピーク時に使える応急処置的テクニック!
【クールダウン術】
• 6秒深呼吸(吸う4秒+止める1秒+吐く6秒)を3セット
• 冷たい水で顔を洗う or 手首を冷やす
• その場から一度離れてみる(トイレに行く/外の空気を吸うなど)
• 怒りや不安を「実況中継」する(例:「今、すごく怒ってる。体が熱くなってる」など)
こうした“その場しのぎの対処”も、とても大事!感情が暴れそうな瞬間を乗り越えるための小技として、ぜひ覚えておいてください。
⸻
思考を整えることは「心の整理整頓」
感情に振り回されやすいと感じるとき、それはあなたが「感情的な人」だからではなく、「思考が絡まりすぎているだけ」かもしれません。
感情を無理に抑え込む必要はありません。でも、その感情がどこからきたのか、どんな考えがあるのかに気づけると、自分で自分を苦しめるクセから少しずつ解放されていけます。
人間関係のストレスから心を守る!境界線の引き方とコミュニケーション術
情緒が不安定になる原因として、ものすごく多いのが「人間関係によるストレス」。職場、家族、友人、恋人――人と関わるなかでのモヤモヤや疲れは、心のコンディションを大きく左右します。しかも厄介なのは、“相手を変える”ことができないってこと!
だからこそ大事なのは、「自分を守るための境界線(バウンダリー)」と「伝え方の工夫」。ここでは、ストレスをためこまないための“人間関係との付き合い方”を、実践的に解説していきます!
⸻
なぜか疲れる人間関係…その正体は「境界線のなさ」
他人に振り回されやすい、気を使いすぎてしまう、NOと言えない…。そんな人に共通しているのが、“自他の境界線”があいまいになっていること。
【例】
• 頼まれると断れず、忙しくても引き受けてしまう
• 相手の機嫌や反応に必要以上に敏感になる
• 「期待に応えなきゃ」と無理してしまう
• 相手の感情や問題を、自分のことのように背負ってしまう
こうした関わり方は一見“優しい人”に見えるけれど、自分の心がボロボロになりやすい危うい状態でもあるんです。
⸻
バウンダリー(心の境界線)とは?
バウンダリーとは、「自分」と「他人」の間にある見えない線のこと。これを意識できるようになると、
• 相手の課題と自分の課題を分けて考えられる
• 無理して合わせたり、抱え込んだりしなくて済む
• 必要以上に責任を感じない
• 感情的な人の影響を受けにくくなる
という風に、心がグッと安定しやすくなります!
⸻
まずは“3つの境界線”を意識してみよう
1. 物理的な境界線
→ 自分の時間・空間・所有物など。「忙しいときは連絡にすぐ返信しない」もこれに含まれます。
2. 感情的な境界線
→ 相手の感情を受け止めすぎず、「それはあなたの感情、私は私」と切り分ける意識。
3. 責任の境界線
→ 「それは私の責任?それとも相手の責任?」と考えて、自分の負担を明確にする。
これらの境界線を意識するだけでも、グッと心が軽くなるんです!
⸻
無理せず心を守る!上手な「NO」の伝え方
「断れない」「嫌われるのが怖い」と感じる人ほど、人間関係で消耗しやすい。でも、無理して我慢しても、結局どこかで爆発してしまったり、自己嫌悪になってしまったりしがちです。大事なのは、柔らかく、でもハッキリ断るスキルを身につけること!
【おすすめの断り方】
• ワンクッション入れる:「気持ちは嬉しいんだけど…」「本当にありがたいんだけど…」
• 代替案を出す:「○日は無理だけど、△日なら大丈夫だよ」
• 自分軸で伝える:「今ちょっと余裕がなくて…」「最近体調崩してて無理しないようにしてるの」
ポイントは、“相手を責めずに、自分の状態を伝える”こと。そうすれば、角も立ちにくく、関係も良好に保てます!
⸻
境界線を保つための「感情的な距離」の取り方
どうしても相性が合わない人、いつも否定的な人、エネルギーを奪ってくるような人っていますよね…。そういう人と関わるときに有効なのが、「感情的な距離」を保つこと。
【実践テクニック】
• 心の中で「この人の言葉は“ノイズ”」とラベリングする
• 反応しすぎず、聞き流す練習をする
• 目の前の言葉に全部反応せず、「自分に関係あることか?」とワンクッション置く
• “その場しのぎの相づち”で切り抜ける(例:「へえ~」「そうなんですね」だけで済ませる)
「全部ちゃんと受け止めなきゃ」はやめてOK!必要なことだけ拾い上げて、あとはスルーで大丈夫です。
⸻
コミュニケーションで心を守る!人との関係をラクにする話し方のコツ
境界線を守りながらも、良好な人間関係を築くには、「伝え方」にもちょっとした工夫が必要です。
【ラクになる話し方のポイント】
• 事実と感情を分けて伝える:「○○と言われたとき、ちょっと傷ついたんだ」
• “私は”を主語にする:「私はこう感じた」「私はこう考えてる」
• 感謝+自分の意見:「助けてもらって嬉しかった。でも、これからは自分でやってみたいと思ってる」
• お願いベースで伝える:「○○してくれたら嬉しいな」「今はこれを優先したいから、△はまた今度にしてもいい?」
こうした伝え方を意識すると、衝突を避けつつ、自分の気持ちや考えをちゃんと守れるようになります。
⸻
「人付き合いは頑張りすぎなくていい」
人間関係に疲れやすい人って、たいてい「良い人であろうとしすぎてる」「ちゃんとしなきゃと思いすぎてる」んです。でも、すべての人とうまくやる必要なんてありません。むしろ、「疲れる関係」と「心地よい関係」を分けて考える勇気こそが、心を守る第一歩。
境界線は冷たさではなく、「自分も相手も尊重するための優しさ」。自分の心を守る選択、もっとしていいんです!
【まとめ】情緒が安定する人は何が違う?心がブレない自分になるために今すぐ始めよう
ここまで読んでくださったあなたはもうお気づきかもしれません。情緒が安定している人って、もともとの性格が穏やかなんじゃなくて、「心の整え方」をちゃんと知っていて、それを日常の中で実践している人なんです。
⸻
情緒が安定している人に共通する5つの特徴
1. 感情と向き合うことを怖がらない
→ 怒りや不安も「悪者」にせず、「今どんな感情かな?」とちゃんと感じてあげられる。
2. 脳とホルモンの仕組みを理解している
→ メンタルの揺れを“気合い”や“根性”で乗り切ろうとせず、体の仕組みに沿ったケアができる。
3. 毎日の習慣を大切にしている
→ 睡眠・運動・食事・呼吸・スマホとの付き合い方まで、自分の「調子が整うパターン」を持っている。
4. 考え方を客観的に見直すクセがある
→ 自分の思考を見つめて、「本当にそうかな?」「今の私はどうしたい?」とセルフカウンセリングができる。
5. 人との距離感を自分で調整できる
→ 無理に誰かに合わせたり、すべてを抱え込まず、「自分の心を守る選択」をきちんとできる。
⸻
「感情の波」はなくならなくていい。でも、のまれない自分になれる!
情緒が安定するというのは、「感情の波がゼロになる」という意味ではありません。むしろ、怒ったり、落ち込んだり、不安になるのは人間として当たり前のこと。
大切なのは、その感情に気づき、振り回されずに扱えるようになること。
• ぐるぐる悩む前に、ひと呼吸置く
• イライラしたら、まず睡眠と食事を整える
• 落ち込んだら、紙に気持ちを書き出してみる
• 頼まれてもしんどい時は、やさしく断ってみる
こうした“小さな選択の積み重ね”が、心の安定を育ててくれるんです!
⸻
最後に:今日からできる「情緒安定アクション」3つ!
1. 朝の太陽を浴びる+3分呼吸を整える
→ セロトニンを増やして、心と体のリズムをリセット!
2. 感情を紙に書き出してみる
→ モヤモヤは“頭の中”じゃなく“紙の上”で整理しよう!
3. 疲れる人・話題・SNSから一歩引いてみる
→ 心のスペースは、自分で守っていいんです!
⸻
情緒が安定している人は、自分に優しく、自分と向き合うことを大切にしています。
あなたも「ブレない自分」を、今日から少しずつ育てていけますよ!
どうか、まずはできることからひとつずつ。一緒に“揺れない心”を作っていきましょう!