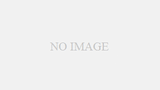日々の労働に携わりながら、契約社員として就業している皆様、そのような身分が存在するがゆえに“差別的な待遇”を受けている経験や不安、いわば使い捨ての概念に当てはめられた経験はないでしょうか?これこそが正社員との違いであり、問題点とも言えます。
私自身が非正規雇用者である契約社員として、しかも4年に及んで働いた経験があります。
その当時、身にしみて感じたのが、「お前は非正規だから」と正社員と差別される待遇、そして、非正規差別の概念に苛まされた時間でした。
その経験があるからこそ、差別から逃れるため、そして自己の価値を上げるためにスキルアップをして非正規から抜け出すべきだという意識へと歩みを進めました。
そして現在は、人間観察能力が評価されて、複数の企業の採用面接担当者として活動しています。
ここで、私からの視点として共有したいのが、採用活動を通じて企業が非正規雇用者にどのような扱いをしているのか、その実態です。
一般的にはなかなか表に出ることのないディープな情報ですが、差別を乗り越えるため、または自己の価値を高めるためのフレームワークとして参考にしていただければ幸いです。
具体的には、企業が非正規雇用者を使い捨ての駒のように扱う背景、そしてそれを回避するため、自身に何を求めるべきかという視点から情報をお伝えします。
どうかあなたの働く環境をより良いものへと進化させるお手伝いができればと思います。
- 契約社員は使い捨て人材?なぜ企業はそうしてしまうのか
- 契約社員の雇用と企業の考え方
- 契約社員の給与はアルバイトと変わらない?企業が見せる使い捨ての態度
- 教育投資の対象外が示す契約社員の扱いについて
- 契約社員が雇用の調整弁として使われる理由に迫る
- 正社員と契約社員の解雇の違いとその理由
- 非正規雇用者への経営者の厳しい視線 – 企業の人事管理における新たな課題
- 契約社員からの無期雇用転換や正社員登用への期待を再考せよ
- 非正規雇用者が”使い捨ての駒”にならないための3つの策
- 使い捨てにならない存在となるためのキズナの育て方
- 契約社員から正規社員への道: その心理的変化を理解する
- 正社員として別の会社に転職する意義とその理由
- 契約社員から正社員への道は厳しいのか:適切な転職へのアプローチ
- 理解して戦うべき「契約社員としての働き方」 – 使い捨て扱いからの脱出方法とは?
契約社員は使い捨て人材?なぜ企業はそうしてしまうのか
契約社員として働いている方々、大変残念なお話ですが、一部の企業ではあなた方を「使い捨てのコマ」とみなしている事実について、お伝えする必要があると思いました。
まず、契約社員という形態の雇用があること自体が、その企業が人材を適材適所に活用しようという姿勢の表れではあります。
しかし、それが「使い捨て」という形になってしまうのは、企業の短期的な利益追求と、雇用形態の柔軟性が生み出す歪みが大きな要因と言えます。
四年間の非正規雇用者の経験と、さまざまな企業の採用担当を任されたことから得た知識をもとに、具体的な理由を解説していきます。
まず一つ目はコスト削減です。
契約社員の給与は一般的に正社員よりも低く、また社会保険負担等のコストも企業側が軽減できます。
また、契約更新の際には、人員の調整が容易であり、業績が低迷した場合などには契約を更新せずに人件費を節約することが可能です。
二つ目は、労働法のギャップであります。
契約社員は正社員と比べて法的な権利が弱く、解雇のハードルが低いです。
また、契約社員は固定期間の雇用であるため、企業が求める業務量と人員の調整が容易です。
こうした現状の中で契約社員として働く人々は、安定した雇用という観点からは厳しい立場に置かれます。
しかし、契約社員が「使い捨て」人材とならないためには、その能力を発揮し、企業にとって不可欠な存在になることが求められます。
企業も、一方的に人材を使い捨てると、雇用の品質や品位を落とすことにつながり、長期的には企業の存続や競争力に悪影響を及ぼすことになるでしょう。
契約社員の活用を進める一方で、その待遇改善やキャリアパスの見直しなど、雇用の安定につながる改革も行っていくべきです。
契約社員の雇用と企業の考え方
まず初めに、契約社員について理解を深めましょう。
契約社員とは、決められた契約期間内で働くことを前提とした雇用形態です。
契約社員は決まった期間、企業に対して労働力を提供します。
その期間が終われば、それで契約は終了となります。
それでは、なぜ企業は契約社員を採用するのでしょうか。
企業が契約社員を採用する理由はいくつかあります。
その中でも主な理由としては、企業が定期的に行なわれる特定のプロジェクトや仕事のために、期間限定で労働力が必要な場合があります。
そのような状況で契約社員を採用すると、企業は必要な人材をタイムリーに手配することができ、それらの仕事を終了させることができます。
しかし、ここで強調したいのは、契約社員の契約書には「契約期間終了後は契約を延長することがある」という記載があることです。
しかし、ここでの「ある」は可能性を示す言葉であり、必ずしも契約が更新されるわけではないのです。
つまり、企業は契約期間の終了をもって、契約社員との関係を解消することを前提としているのです。
契約社員という立場は、一生働いてもらうことを前提とした雇用形態ではないということを認識しておくことが重要です。
一部の人々にとっては残酷に思えるかもしれませんが、これが事実です。
企業が契約社員を採用する際、その前提には期限付きの労働力提供という考えが含まれているのです。
言い換えると、契約社員制度は、企業にとっては人材の「使い捨て」を可能にする立場ともいえるのです。
契約社員の給与はアルバイトと変わらない?企業が見せる使い捨ての態度
近年、多くの企業が契約社員を事実上の消耗品と見なして扱っているという事実があります。
それに大きな理由の一つが、給与の問題です。
一見すると、契約社員は正社員と同じように月給制なので、見た目は同等のように思われます。
ですが、よく見てみると、時給に換算した場合にはアルバイトと変わらない底辺労働者としての待遇が待っているのです。
その計算は、所得総額を一年の労働時間で割ることで出せるもので、210万円の年収で月175時間働くとしたら、その時給は大体1,000円ほどになります。
これは一般的なアルバイトと変わらない額です。
この節約志向の背景には、企業が利益を最大化しようと安価で労働力を使いたいと考えているからなのです。
だからこそ、正社員にはボーナスを支払う一方で、契約社員には支払わない取り扱いもあるのです。
このような給与のずれは、2020年から施行された「同一労働同一賃金」の法律に明らかに違反しています。
しかしながら、それを無視し続ける企業は少なくありません。
これらからも明らかに、企業が契約社員を非正規労働者として使い捨てるための「駒」として扱っていることがわかります。
この現実を知った上で、私たちは何ができるのか、何をすべきなのかを深く考えるべきでしょう。
正社員と名のつく契約社員でも給与がアルバイトレベルであるなど、働く環境には厳然たる現実があります。
それに目を向け、うまく職場選びをすることが求められます。
教育投資の対象外が示す契約社員の扱いについて
本文では契約社員の教育に関して企業がどのような行動を取っているか、そしてそれが何を意味するのかを検討します。
契約社員というのは、専門職以外では大抵の場合、単純作業や肉体労働など、特に特別な技術や知識を必要としない仕事を任されることが多いです。
そのため、長年連続して同じ職場で働くようなことがあっても、それがキャリアとして評価されたり、新たなスキルを身につけるための機会になることはほとんどありません。
この背景には、企業が契約社員に対する教育投資を控えている状況があります。
そもそも契純作業を担当する人材を雇用するために契約社員を採用する企業側にとって、作業以上の仕事が出来る人材に育て上げるための教育投資を行う必要性は低いと考えられているのです。
しかしながら、このような状況は企業が契約社員を使い捨てのコマ、つまり長期的な投資価値がないと評価していることを示唆しています。
組織の持続可能性を高めるためには、人材育成が不可欠です。
それにも関わらず、多くの企業は契約社員に対して教育投資を行わず、その持続性の一部を危険にさらしていると言えます。
また、このような行動は契約社員が企業にとって本当に重要な役割を果たす可能性を限定してしまうだけではなく、彼ら自身のキャリア建設のための機会も奪ってしまっています。
契約社員が雇用の調整弁として使われる理由に迫る
まず最初に、一般的に「契約社員」という存在が何によって生み出され、どのような立場にあるのかを理解しておきましょう。
彼らは会社と労働者の間に立ち、雇用契約を結び、一定期間の勤務を約束する存在です。
つまり、彼らと会社の間には契約という法律上の関係性が生じます。
それでは、なぜこの契約社員が雇用の調整弁として使われるのでしょうか。
これは、契約期間や待遇といった点において、正社員に比べて柔軟性があるからだと言えます。
つまり、会社には契約社員に対して自由な調整が可能という利点があります。
具体的には、会社が業績不振や構造改革を必要とした場合、一定の契約期間が終了した契約社員を再雇用せず、人件費を抑えることが可能です。
また、業績が好転した時には追加で人員を確保することも容易で、それによって業務量の変動をスムーズに吸収することができます。
このように、これら雇用形態の社員は雇用調整弁として機能し、会社の業績に合わせて人員を調整する役割を果たしているのです。
しかし、一方でその柔軟性が裏目に出て、使い捨ての駒として見られる側面も否めません。
プロジェクト終了や業務量の減少などにより、いとも簡単に契約を打ち切られる可能性もあるからです。
そのため、契約社員たちは不安定な立場に置かれ、雇用の安定を求めて常に戦っている状況があります。
この事実を理解した上で、働く側としても会社側としても、契約社員という雇用形態をどのように捉え、どのように扱うべきかを再考することが重要となります。
正社員と契約社員の解雇の違いとその理由
正社員と契約社員、この二つは日本の会社においてよく見られる働き方ですが、それぞれの雇用形態には大きな違いがあります。
その筆頭ともいえるのが、解雇のハードルの違いです。
まず、契約社員は簡単に首を切れるという認識が日本の労働現場には存在します。
これは契約社員には契約期間が存在し、この期間が満了した場合、その契約を終了させることが可能であるという法律上の規定によるものです。
一方、正社員は一般的に解雇が難しいとされています。
これは労働法を始めとする法律の規定により、正社員を解雇するためにはある程度の条件を満たす必要があるからです。
具体的には、解雇四要件と呼ばれる以下の条件を満たさなければ、正社員を解雇することは認められないのです。
1. 人員整理の必要性 2. 解雇回避努力義務の履行 3. 被解雇者選定の合理性 4. 解雇手続きの妥当性 すなわち、解雇をするためには、解雇する必要性があるか、会社として解雇を回避するための努力を行ってきたか、被解雇者の選定は合理的であったか、解雇のための手続きが適切であったか、といったことが詳細にチェックされるのです。
このような厳重なチェックがあるため、経営状況等により人件費を削る必要が生じた場合、解雇のハードルが低い契約社員がまず狙われることが多いと言えます。
大切なのは、その背景にある法律の違いを認識し、各位の個々の働き方に合わせた雇用形態を選ぶことが求められます。
非正規雇用者への経営者の厳しい視線 – 企業の人事管理における新たな課題
本日、我々が取り組むべき課題について考察を深める目的で、現代の企業運営におけるある特異な現象を取り上げたいと思います。
そのテーマは、多くの経営者が非正規雇用者に対して不公平で蓋然性の高い態度を示す傾向にあることです。
以前私が所属していた会社の経営者もその一人でした。
彼は正社員の雇用保障に対しては絶対的な信念を持っており、その安定を犠牲にすることは一切せず、全ての決定をその原則に基づいて行いました。
しかしながら、非正規雇用者についてはおおよそ逆のアプローチをとり、業績が悪化の兆しをみせるとすぐに解雇するという手段を採りました。
私自身がその流れの一端であり、我々の契約終了はその直後に続きました。
解雇が行われるとき、あるひどい発言が私の耳に入ってきました。
「あいつらは正社員じゃないから、大丈夫だろう」。
彼がそう言ったと共僚から聞いたとき、驚きと怒りの念によって一時的に我を失いそうになりました。
これらの経験から、「非正規雇用者は正社員と比較して劣っているから扱いが雑になる」という一般的な態度が経営者の間で存在することは明らかです。
しかし、この「正社員と非正規雇用者の間の違い」を根拠にした冷酷さは、公正な労働の場を建設するという目標から我々を逸脱させ、非正規雇用者に心理的な厳しさをもたらすだけでなく、企業の生産性や総合的なパフォーマンスにも無視できない影響を及ぼします。
経営者が非正規雇用者に対する態度の修正を考慮に入れるべき時期がきています。
そのためには、正社員と非正規雇用者の間に存在する橋渡しをする役割や仲裁者などの新たなロールを作り出し、それによって企業の内部で平等な人材管理と労働環境を創出し、全ての雇用者の能力を最大限に引き出すのが求められます。
それは大変な課題であり、しかし、経営者が直面しなければならない重要な問題だと断言できます。
契約社員からの無期雇用転換や正社員登用への期待を再考せよ
現在、契約社員としてお勤めの皆様、未来の正社員への転職、あるいは無期雇用への切り替えを切望していることかと存じます。
その努力を否定するものではありませんが、採用に関わる側からの視点で申し上げますと、契約社員が無期雇用、あるいは正社員として採用されることは極めて特例的な事案になります。
以下にその理由について解説します。
契約社員という雇用形態の本質について理解することが、この視点を理解するための第一歩となります。
多くの企業が契約社員を雇う主な理由は、特定の期間、特定の業務を行ってもらうことにあります。
これが企業側の契約社員への基本的な考え方であり、期間が来れば契約は終了となります。
これは一見適当に思えるかもしれませんが、あくまで経済的な観点や経営戦略から見た雇用のあり方です。
これとは対照的に、正社員登用や無期雇用に転換すれば、その企業は労働者を永続的に雇用するという意思表示を明示したことになります。
すなわち、期間終了後に契約を解除する機会がなくなることを意味します。
この契約更新の権利がなくなることは企業側のリスクを増大させるため、企業としては極力避けたがる傾向にあります。
このような事例から、多くの企業が優れいた個々の契約社員に対しても無期雇用転換や正社員登用を推進しようとはしないという現状があります。
これは契約社員の能力を否定するものではなく、あくまで企業の戦略と立場から見た現実的な考え方です。
したがって、契約社員である皆様に対し、無期雇用転換や正社員登用を強く望んでいる方は、自分がなぜ契約社員であるのか、自分の存在が企業にとってどのような価値をもたらしているのかを理解し、そのうえで現状を再評価することをお勧めします。
最終的には、自身のキャリアアップのために企業が提供するチャンスを見つけ、それを最大限に活用することが重要であると思われます。
非正規雇用者が”使い捨ての駒”にならないための3つの策
この記事は、契約社員などの非正規雇用者が企業側から使い捨ての駒として扱われる背景と、そのような状況を避けるための三つのポイントを主なテーマとしています。
非正規雇用者たちが企業から雑に扱われやすい理由としては、一時的な職務配置の変更や人員調整のツールとしてみられてしまうことが挙げられます。
これらの状況の中で自己を守るためには、自身が「使い捨ての駒」とみなされないような行動を心掛けることが不可欠です。
まず第一に、自己価値を常にアップデートし、自分のスキルや経験を高めることです。
非正規雇用者として働く中で、日々の業務をこなすだけではなく、自己を向上させるための学習やスキルの磨き方を模索することが重要です。
それは新たな技術の習得から専門知識の深化まで、自己の職業人としての価値を向上させることができます。
第二に、コミュニケーション能力を磨くことです。
社内のチームや部署間でスムーズなコミュニケーションを図れる能力は、職場での立場や評価に大きな影響を与えます。
人間関係の構築や情報共有、問題解決など、多様な場面でのコミュニケーション能力は、自分が会社の一部であると認識され、価値ある存在と見られるために不可欠な要素です。
最後の第三のポイントは、自己主張と交渉力です。
自身の意見を適切に伝え、自分の立場や要求を守る能力は、使い捨てられない存在として見られるために大切です。
自己主張が強すぎて他者を反感を買うこともないよう、適切なタイミングと方法での発言が求められます。
また、自己の利益を最大化するためには、交渉力も欠かせません。
自己の要求や条件を相手に理解してもらう能力は、良好な労働環境を維持するために重要です。
これら三つのポイントは、非正規雇用者が使い捨ての駒として扱われないための手段として提案されます。
自身の価値を高め、他者との関わり方を改善し、自身の利益を守るだけでなく、企業が自分を価値ある存在と認識するために不可欠な行動です。
経済環境の変化に伴い、雇用形態が多様化している中で、自己の立ち位置を確立するためには、これらのポイントを意識することが求められます。
使い捨てにならない存在となるためのキズナの育て方
私がこれまでに獲得してきたキャリアの中で最も大切だと思う教訓の一つは、自分自身が企業にとって「替えのきかない存在」になることの重要性です。
どのような雇用形態であれ、自分自身が必要とされる存在になることで、個人のキャリアの安定性と社内での影響力が大きく増すことを私自身の経験を通じて学んできました。
まず、なぜ一部の非正規雇用者が「使い捨て」と見られるのかについて考えてみましょう。
それは非正規雇用者が任される業務が誰でも可能な業務であるため、その雇用者が辞めても他の人を雇えば会社が問題なく機能すると考えられているからです。
では、この状況を逆転させてみるとどうなるでしょう?つまり、もし皆さんが社内で「私がいなければ困る」と思われるような存在になれば、契約社員であっても使い捨ての駒とは思われなくなります。
これが私が皆さんに伝えたいメッセージです。
私の経験をお話ししますと、過去に私が契約社員として働いていた会社では、新規事業の立案と運営、そして人事評価制度の整備を一人で行っていました。
その新規事業は成功裡に黒字に転換し、私が策定した人事評価制度も採用され、その全運営が私に任されていました。
この事業や制度の全体像を理解しているのは私だけでした。
この結果、私は契約社員でありながらも「辞めると大変なことになる」と思われ、社内で最も発言力のある一人になり、正社員へのオファーも何度も受けました。
しかし、当時の会社の方針に合わないと感じていたため、よりフレキシブルに動ける契約社員として働き続けることを選びました。
私のケースは極端な例かもしれませんが、皆さんも仕事に対する前向きなエネルギーと努力を持つことで、必要不可欠な存在になることが可能です。
そして、「使い捨て」ではなく、「替えのきかない存在」として扱われるようになることも十分に可能です。
今後のキャリア形成のヒントにしていただければ幸いです。
契約社員から正規社員への道: その心理的変化を理解する
再確認することになりますが、契約社員が「使い捨て」とされる根本的理由の一つは、彼らの雇用が一定の期間に制限されていることにあります。
その存在があるために、契約社員は契約期間中だけ企業に留まる人物とみなされる傾向があります。
これが契約社員が日々感じる”使い捨て”という感覚の原因の一つとなります。
しかし、一部の優秀な契約社員には雇用形態を変えるチャンスがあります。
それは、正社員へのオファーを得るというものです。
通常、企業は正社員として雇用する人物に対して定年まで働いてもらうことを前提に、その雇用条件を練ります。
したがって、正社員に昇進することは、使い捨ての駒のように扱われるという状況からの免除を意味します。
労働者のパフォーマンスが変わらないにも関わらず、雇用形態が変わるだけでその扱いが大きく変わることは不思議な現象かもしれません。
しかし、これは組織の中に存在する「雇用形態に基づく心理的な認識」によるものであり、また労働者自身が持つ、「自分の位置づけ」に関する心理状態も影響を及ぼします。
そのため、契約社員が正社員になるためには、ただ単に作業をこなすだけでは足りません。
必要なのは、正社員登用を打診されるだけの価値を見出すことができる高いパフォーマンスを発揮することです。
さらに、そのパフォーマンスを維持し続ける意志と努力、組織における自身の存在価値を高め続ける能力も求められます。
正社員への昇格は、使い捨てという状況からの脱出や定年までの雇用安定といった明らかな利点がある一方で、それは組織の一員としての役割と責任も増大することを意味します。
それは、使い捨ての駒のように見られるだけではなく、組織の一員としての存在価値と役割が求められるようになるという新たな課題をもたらします。
しかし、その課題を乗り越えることができれば、一部の優秀な非正規社員が成し得る、正規社員への道が広がります。
そして、その道のりは決して容易ではありませんが、その先には雇用の安定と、社員としての自己実現が待っています。
正社員として別の会社に転職する意義とその理由
使い捨ての労働力として扱われることは、誰しもが避けたい状況だと言えるでしょう。
しかし、現在の仕事環境で自身がそのような立場に置かれてしまっている場合、その状況を改善するためにはどのような方法が考えられるでしょうか。
その対策として最も手に取るべきものこそ、他の会社へ正社員として転職することです。
では、なぜ使い捨ての労働力として扱われてしまう状況から脱却するために、転職という選択肢が最善と言えるのでしょうか。
その理由は主に二つあります。
第一に、正社員として他の会社に転職することで、新たな仕事環境に身を置く機会を得られます。
新しい会社には新しいポリシーや独自の文化、新しい同僚が待っており、それらに触れること自体が自身の視野を広げるチャンスになります。
また、その会社が労働者の待遇や働きやすさに注力している場合、使い捨ての労働力として扱われることを防ぐ霊感が可能になります。
特に労働者への敬意や人権尊重を企業文化として大切にしている会社では、使い捨てられることなく、安定した働き方が可能となるでしょう。
第二に、正社員として的場へ切り替えることにより、自身のスキルや経験を高価値のものに変えるチャンスを得ることができます。
使い捨てられる人材は、あなたが何か特殊なスキルを持っていないといった理由だけでなく、その扱いに問題がある会社の文化や環境によるものだとも言えるでしょう。
新たな会社で新たな役職に就くことで、あなた自身の能力が正当に評価される環境を手に入れることができます。
その結果、自身のスキルや経験が社会的に価値あるものと認識され、自己価値の向上につながります。
転職は大きな決断を必要としますが、それは新たな道への一歩とも言えます。
使い捨てられるような状況に立たされた時点で、それはあなたが今いる環境があなた自身を正当に評価していない、もしくはあなたの能力を十分に活用できていないという状況を示しているのです。
こうした理由から、使い捨ての駒のように扱われることから逃れ、自身の能力を存分に発揮するためには、他社への転職という選択肢を真剣に考えることが一番です。
契約社員から正社員への道は厳しいのか:適切な転職へのアプローチ
従業員の雇用形態は収入だけでなく、社会保障や職場環境にも深く関与しています。
そのため、職種が契約社員である場合、無期雇用や正社員となる可能性は常に考慮にいれられます。
しかし、それは必ずしも容易な道のりではないかもしれません。
多くの企業は重要な業務に対する不確実性を避けるため、雇用条件を変更することに消極的です。
これは、それが当面のコスト削減に結びつく場合でも同様です。
契約社員が使い捨てと見られる根幹的な理由は、その雇用契約に定められている期間限定の雇用であることです。
つまり、期限という要素が労働環境に一定の制約をもたらします。
それゆえ、雇用期間が存在しない無期雇用や正社員への転換が最も効果的な解決策となります。
しかし、その変更を求めても、上記の理由からなかなか雇用形態の変更は叶わないのが現実です。
そのため、自身のキャリアを見つめ直し、他の会社で直接正社員として雇われる道を選ぶべきです。
ただし、その選択をする際には、あなたが持っている経験やスキルが、新しい雇用先で価値を生み出せるかどうかを慎重に考慮する必要があります。
私自身の経験から言えることは、契約社員としてのスキルや経験を正社員雇用という形で移動させることが困難ではないということです。
実際、自身が契約社員から正社員へという雇用形態で他社に転職成功した経験を持っています。
従業員の価値は、その人が持つスキルや経験だけでなく、その能力が戦略的に活用できる場所に大きく依存します。
したがって、雇用形態の改善を望む場合には、その価値を正当に評価し、活用できる場を見つけ出せるかどうかが重要になります。
これは、職場を探すだけでなく、あなた自身がどのように価値を提供できるのか理解し、その価値を明確に伝える能力にも依存します。
今まさに、あなた自身が自分のキャリアについて考え、次の一歩を踏み出す最適な時期かもしれません。
理解して戦うべき「契約社員としての働き方」 – 使い捨て扱いからの脱出方法とは?
契約社員として働く方たちが、”使い捨ての駒”として捉えられがちであるとの問題について述べたいと思います。
そして、そのような状況から抜け出すための具体的なステップもお伝えします。
多くの企業は、契約社員を長期に渡って雇い続けることはありません。
その理由の一つに、雇用期間の存在が挙げられます。
契約社員はその名の通り契約期間が決められており、それが終了すれば企業は契約の更新をせずに解雇することが可能です。
これにより、契約社員は企業が雇用を調整するための弁となってしまいます。
また、契約社員の収入はアルバイトと同等、あるいはそれ以下であることも少なくありません。
さらに、正社員とのあいだで法律的に禁止されている不合理な賃金や待遇の差が存在する企業も一定の割合で存在します。
そして、多くの企業は契約社員からの正社員への登用や無期雇用転換を神経質に考えています。
では、ここからが本題です。
契約社員として”使い捨ての駒”から抜け出し、自身のキャリアを築くためにはどうすればいいでしょうか。
主に以下の3つの方法が挙げられます。
1. 企業が手放すことのできない、特別なスキルや経験を持つようになる 2. 優れた業績を上げ、正社員へのオファーをもらうような働き方をする 3. 現職に見切りをつけ、他社で正社員として再スタートを切る これらのポイントを抑えておけば、ますます自身のキャリアに成功をもたらすことでしょう。
最後に付け加えるならば、”使い捨て”と誤解されないためには、一貫して誠実に働き、自身のスキルを向上させることが極めて重要です。
社内外での評価を高めることは、自身の働きぶりを一層引き立て、自身の幅を広げます。
私自身、社内および社外での評価を上げた結果、契約社員から正社員への道を選択することができました。
もし、あなたが現職の契約社員として使い捨てのような扱いに耐えかねているのであれば、スキルアップに一層の努力を注ぎ、自身の労働を改善することを強くお勧めします。
私たちはあなたが自社において敬意を持って扱われる存在となることを心から祈っています。